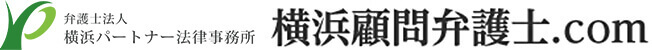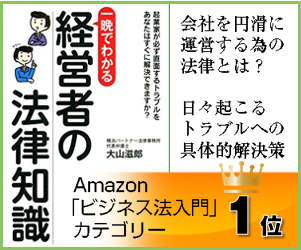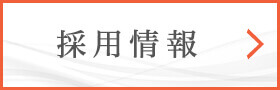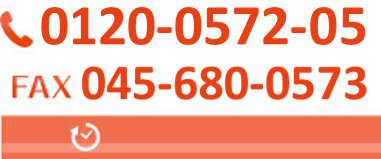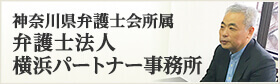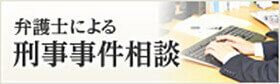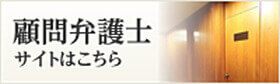会社に役立つ刑事豆知識(4)
今回も、社内で盗難が生じたときに、会社としてどう対処していくのが良いかについて考えていきましょう。
今回は、その場にいる人に対し、持ち物検査をすることを想定し、そこでの注意点を解説します。
まず、前提として、会社が持ち物検査をするのと、警察が職務の一環で所持品検査をするのとでは、自ずと権限の強さが異なります。
判例を比較しても、警察の権限のほうが強いとはいえ、やはり会社には、ある程度捜査に任せるというスタンスが大事であるように思います。
ですが、状況によっては、その場で荷物検査をすれば犯人が見つかるかもしれない、また、抜き打ち的な検査をする必要が出てくる場合もあるでしょう。
そのような検査で問題になるのが、従業員のプライバシーの権利を侵害しないかどうかです。検査をする際に、従業員それぞれに同意をとり、任意で行うのであれば、問題はないでしょう。
では、持ち物検査をする際に、拒否をする従業員がいるときに、その従業員に強制的に所持品検査を行うことはできるのでしょうか? 答えは、ほぼできません。
会社による所持品検査が問題になった裁判例で、①検査をする合理的な理由があり②一般的に妥当な方法と程度で③制度として全従業員に対して画一的に行われており④就業規則その他明示の根拠に基づき行われていれば、従業員は所持品検査を受ける義務を負うということが判断されたことがあります。
逆に言えば、就業規則などに定めていなければ所持品検査を強制する前提を欠きますし(④)、相手を押さえつけて検査することは、一般的な方法と程度ではないため(②)、違法になってしまうでしょう。
現場全員に分け隔てなく確認をとり、検査は従業員の無実を証明するためにも役立つ点をご説明されたうえ、同意した従業員に実施するというのがベターでしょう。
物好き弁護士のつぶやき
窃盗罪のアレコレについて、少し触れておこうと思います。
窃盗罪には、いろいろな行為が含まれます。万引き、すり、置き忘れた物を拾ってしまう行為も窃盗罪になりえます。権限がないのに他人のカードを使ってATMから現金をおろすと、銀行に対する窃盗罪が成立すると言われています。
軽度な万引きでも、繰り返し検挙などされればやがては送検され、罰金刑になる可能性があります。そのような場合には、刑事弁護人は被害者や被害店舗と示談交渉をすることで、不起訴を目指します。 (2022年12月6日 文責:原田大士)
- 英文契約書のアレコレ(5)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第16回 セクハラ相談窓口への通報への対応が甘かったら・・・?
- 【事業承継編】拒否権付株式(黄金株)は本当に有効なのか?
- 退職に関するトラブルについて(19)
- 知って得する労働法改正⑤
- 労働事件裁判例のご紹介⑤
- 英文契約書のアレコレ(4)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第15回 プライベートで飲酒運転した従業員でも解雇できない?
- 【事業承継編】本当に会社は300万円で買えるのか?
- 退職に関するトラブルについて(18)
- 知って得する労働法改正④
- 労働事件裁判例のご紹介④
- 英文契約書のアレコレ(3)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第14回 無許可残業であっても給与が発生する・・・?
- 【事業承継編】赤字や債務超過の会社でも売れるのか?
- 退職に関するトラブルについて(17)
- 労働事件裁判例のご紹介③
- 英文契約書のアレコレ(2)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第13回 放送事故を起こした社員を解雇したら無効に・・・?
- 【事業承継編】悪質な買い手にご注意!その見極め方と対策
- 知って得する労働法改正③
- 労働事件裁判例のご紹介➁
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第12回 「管理監督者」だから割増賃金を支給していなかった・・・?
- 【事業承継編】高額な価格を提示してくれる会社がよいのか
- 退職に関するトラブルについて(16)
- 知って得する労働法改正➁
- 労働事件裁判例のご紹介
- 英文契約書のアレコレ(1)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第11回 就業規則を周知していなかったため無効に・・・?
- 【事業承継編】買い手はどこまでの価格を提示できるのか?