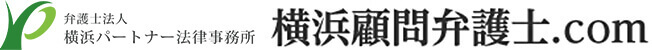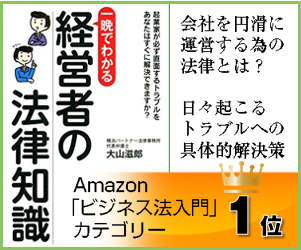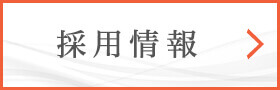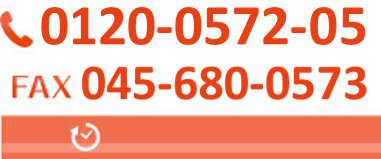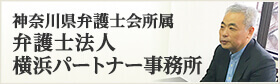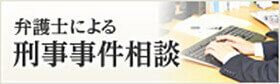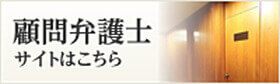請負契約をめぐる注意点
現代の事業活動においては、様々な場面で多種多様な契約形態が用いられています。その中でも、請負契約は特によく用いられる契約形態だと思われます。雇用契約ではなく請負契約とすることで労使双方にとってより自由な働き方が可能となったり、企業間でも請負契約とすることで柔軟な事業活動が可能となるのど、活用の場面が多くあります。
一方で、その利便性から、法の規制をすり抜ける目的で請負契約を利用する(又は知らず知らずのうちにすり抜けてしまっている)場面も見られ、国としてもこれを防止するための法律を整備しています。そのため、請負契約を活用する会社は、請負契約とすることが法律上問題とならないか、しっかりと確認する必要があります。
今回からは、会社が請負契約を活用する際に特に注意すべき点について解説していきます。
今回は「偽装請負」への注意です。
偽装請負とは、契約の見た目上は請負契約などの契約形態としながら、その実態が労働者派遣となっているものを指します。
例として、発注会社と受注会社が請負契約を結び、受注会社の労働者が発注会社において何かしらの業務を行う場合を想定します。このとき、労働者が受注会社からの指揮命令を受けながら業務を行うのであれば、基本的には請負契約となります。一方で、労働者が発注会社からの指揮命令を受けながら業務を行ってしまうと、これは労働者派遣とみなされるおそれがあります。
つまり、契約書の名称がきちんと請負契約となっていることが重要なのはもちろん、それだけでなく、実態としても請負契約となっていること(受注会社が指揮命令していることなど)が非常に重要であるということです。
そして、偽装請負であるとみなされると、受注者と発注者それぞれに、労働者派遣法による罰則等が科される可能性もあります。
そのため、会社としては、発注者側でも受注者側でも、偽装請負になっていないか注意する必要があるのです。
しかし、実態に基づいて判断するといっても、その基準などが分からなければ、会社としても気を付けようがありません。そこで、次回以降は厚労省や労働局が公表している見解等を参照しつつ、具体的にどのようにして注意すべきかを解説していきます。
Atty’s chat
先月、奈良県へ旅行へ行ってきました。吉野山の千本桜が目当てでしたが、うまく開花時期にあたり、見事な桜を鑑賞することができました。奈良市内も満開の時期で、どこに行っても桜という贅沢な旅行でした。京都と違って外国人観光客が少なく、どこも落ち着いて観光できたのもよかったです。 (2025年5月9日 文責:越田 洋介)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第16回 セクハラ相談窓口への通報への対応が甘かったら・・・?
- 【事業承継編】拒否権付株式(黄金株)は本当に有効なのか?
- 退職に関するトラブルについて(19)
- 知って得する労働法改正⑤
- 労働事件裁判例のご紹介⑤
- 英文契約書のアレコレ(4)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第15回 プライベートで飲酒運転した従業員でも解雇できない?
- 【事業承継編】本当に会社は300万円で買えるのか?
- 退職に関するトラブルについて(18)
- 知って得する労働法改正④
- 労働事件裁判例のご紹介④
- 英文契約書のアレコレ(3)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第14回 無許可残業であっても給与が発生する・・・?
- 【事業承継編】赤字や債務超過の会社でも売れるのか?
- 退職に関するトラブルについて(17)
- 労働事件裁判例のご紹介③
- 英文契約書のアレコレ(2)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第13回 放送事故を起こした社員を解雇したら無効に・・・?
- 【事業承継編】悪質な買い手にご注意!その見極め方と対策
- 知って得する労働法改正③
- 労働事件裁判例のご紹介➁
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第12回 「管理監督者」だから割増賃金を支給していなかった・・・?
- 【事業承継編】高額な価格を提示してくれる会社がよいのか
- 退職に関するトラブルについて(16)
- 知って得する労働法改正➁
- 労働事件裁判例のご紹介
- 英文契約書のアレコレ(1)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第11回 就業規則を周知していなかったため無効に・・・?
- 【事業承継編】買い手はどこまでの価格を提示できるのか?
- 退職に関するトラブルについて(15)