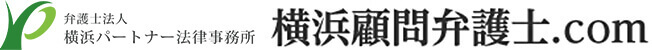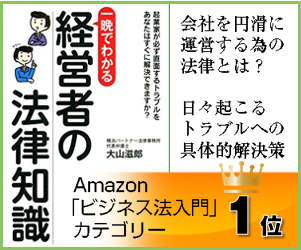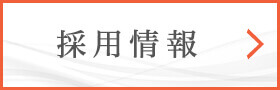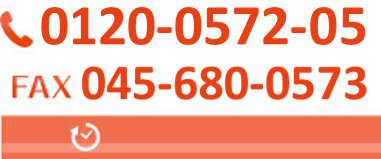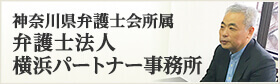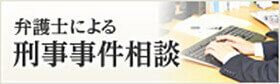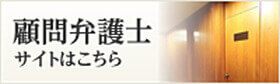第6回 ハラスメント防止と言っても、具体的に何をすべき?
このところ連続で「セクハラ」「パワハラ」「マタハラ」についてお話させていただいてきました。そしてその中では「会社が、ハラスメント発生を防止しなければならない」という点について連呼させていただきました。そこで今回は、実際に会社側がどういう防止策をとるべきなのかについてお話させていただければと思います。
ハラスメントを事前に防止するための具体策としてまず第一には、会社内の会議や全体メールなどで、ハラスメント防止についての周知を行うことです。また、厚労省などが出しているポスターを社内に掲示したり、メールで全体送付しておくという方法もあります。当たり前に感じてしまいますが、意外と、まだまだハラスメントという概念を特に意識していない方も多いもので、予想以上に効果的だと思います。
また、弁護士や社会保険労務士など、ハラスメントに関する専門家を呼んで、ハラスメント防止セミナーを行うという手段もあります。セミナーをやったからといってすぐにハラスメントが無くなると考えるのは楽観的ですが、こういった小さな積み重ねから、従業員もハラスメントへの意識が強まっていくことと思います。
さらに、少しでも早い段階でハラスメントの芽を摘んでおくという意味で「社内相談窓口」を設置しておくこともとても有効です。社内の幹部や人事・労務責任者などに、従業員が相談できる窓口を設置しておくのです。もちろん、被害者だけでなく、その周囲の目撃者などから情報提供が得られることもあります。メールなどで、かつ匿名でも良いとしておくと、かなり有効な情報が得られることが多いと思います。
どの方法も「それ一つで絶対に効果的」というわけではないと思いますが、様々な方法の組み合わせで、従業員が少しでもハラスメント意識を高めてくれることを願って、積極的にハラスメント防止策を講じていきたいところです。
弁護士の徒然草
最近インターネット上で見た中で、一番「なんじゃそりゃ。。。」と思ったハラスメントは、「ヌーハラ」です。「ヌーハラ」だけですぐに何のことかわかる方は…いらっしゃるのでしょうか?
これは…「ヌードル・ハラスメント」の略だそうで、ヌードル(麺)をズルズル吸うことがハラスメントという主張のようです。会社内で業務中にいつもズルズルと麺をすすったり、まさか会議中に麺をすすってたらそれは問題ですが、このサイトの「ヌーハラ」は、ラーメン屋で昼食をとっているようなイラストと共に紹介されています。
日本蕎麦などを音を立てて吸う(風味を一緒に吸い込むということらしいですね)のは一種の日本の文化のようなものですし、あまり何でもかんでもハラハラハラハラ言うのは問題です。 (2022年9月5日 文責:佐山洸二郎)
- 英文契約書のアレコレ(5)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第16回 セクハラ相談窓口への通報への対応が甘かったら・・・?
- 【事業承継編】拒否権付株式(黄金株)は本当に有効なのか?
- 退職に関するトラブルについて(19)
- 知って得する労働法改正⑤
- 労働事件裁判例のご紹介⑤
- 英文契約書のアレコレ(4)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第15回 プライベートで飲酒運転した従業員でも解雇できない?
- 【事業承継編】本当に会社は300万円で買えるのか?
- 退職に関するトラブルについて(18)
- 知って得する労働法改正④
- 労働事件裁判例のご紹介④
- 英文契約書のアレコレ(3)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第14回 無許可残業であっても給与が発生する・・・?
- 【事業承継編】赤字や債務超過の会社でも売れるのか?
- 退職に関するトラブルについて(17)
- 労働事件裁判例のご紹介③
- 英文契約書のアレコレ(2)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第13回 放送事故を起こした社員を解雇したら無効に・・・?
- 【事業承継編】悪質な買い手にご注意!その見極め方と対策
- 知って得する労働法改正③
- 労働事件裁判例のご紹介➁
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第12回 「管理監督者」だから割増賃金を支給していなかった・・・?
- 【事業承継編】高額な価格を提示してくれる会社がよいのか
- 退職に関するトラブルについて(16)
- 知って得する労働法改正➁
- 労働事件裁判例のご紹介
- 英文契約書のアレコレ(1)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第11回 就業規則を周知していなかったため無効に・・・?
- 【事業承継編】買い手はどこまでの価格を提示できるのか?